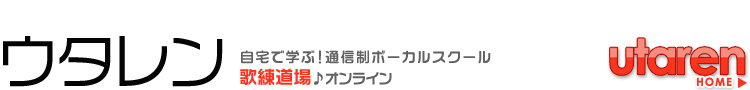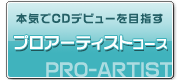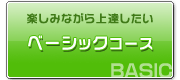あいうえ音楽理論 for ボーカル
2.音符と休符、拍子

では次に音符の仲間たちを紹介しましょう。
音符の種類によって何を表すかというと、「音の長さ」をあらわします。
では、この表をみてください。
音符 |
名前 |
読み方 |
長さ |
全音符 |
ぜんおんぷ |
4拍( |
|
 |
2分音符 |
にぶおんぷ |
2拍( |
 |
4分音符 |
しぶおんぷ |
1拍 |
 |
8分音符 |
はちぶおんぷ |
1/2拍( |
 |
16分音符 |
じゅうろくぶおんぷ |
1/4拍( |
 |
32分音符 |
さんじゅうにぶおんぷ |
1/8拍( |
表の上にいけばいくほど、音は長くなります。
そしてこの音符に符点(.)をつけると1.5倍の長さにすることができます。読み方は「ふてん~ぶおんぷ」と読みます。
![]() =
=![]() +
+![]() (1.5=1+0.5) 符点4分音符
(1.5=1+0.5) 符点4分音符
![]() =
= ![]() +
+![]() (3=2+1) 符点2分音符
(3=2+1) 符点2分音符
![]() =
= ![]() +
+![]() (0.75=0.5+0.25) 符点8分音符
(0.75=0.5+0.25) 符点8分音符
という感じです。
ではここでちょっと問題。
![]() +
+ ![]() =?
=?
1.5+0.5=2ですから、
![]()
2分音符ですね。
![]() +
+ ![]() はどうでしょう?
はどうでしょう?
![]() は2分音符の1.5倍だから「3拍」分で、
は2分音符の1.5倍だから「3拍」分で、![]() は「1拍」だから合わせて「4拍」。
は「1拍」だから合わせて「4拍」。
答えは![]() (全音)ですね。
(全音)ですね。
慣れないと難しいかもしれませんが、最初は紙に書いてゆっくり考えてみてください。
8分音符や16分音符、32分音符が続けて出てくる場合では次のようにつなげます。これを「連符(れんぷ)」といいます。
![]() +
+![]() =
=![]()
![]() +
+![]() +
+![]() +
+![]() +=
+=![]()
![]() +
+![]() +
+![]() +
+![]() +
+![]() +
+![]() +
+![]() +
+![]() =
=![]()
突然ですけど、「バ・ナ・ナ・バ・ナ・ナ・・・」と均等のリズムで声に出してみてください。
できれば「バ」の位置にアクセントをおくか、手拍子をしながらやるといいです。
この「バナナ」という言葉を1拍だとすると、「バ」「ナ」「ナ」はそれぞれ1拍を3つに均等に分けた長さでなります。
このように1拍を均等に3つに分けたリズムを「3連符」といい、
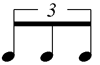 のように表記します。
のように表記します。
連符は、3つだけじゃなくて、5とか6とか9とかいくつでも構いません。
それらは
「5連符」「6連符」・・・と呼びます。
以上のように、これらの音符や符点を織り交ぜながら、色々なリズムを表現します。
休符
次に休符の仲間を見てみましょう。
休符も音符とは逆に「音のない長さ(休みの長さ)」をあらわします。
では 表をみてみましょう。
音符 |
名前 |
読み方 |
長さ |
全休符 |
ぜんきゅうふ |
4拍( |
|
 |
2分休符 |
にぶきゅうふ |
2拍( |
 |
4分休符 |
しぶきゅうふ |
1拍お休み |
 |
8分休符 |
はちぶきゅうふ |
1/2拍( |
16分休符 |
じゅうろくぶきゅうふ |
1/4拍( |
|
32分休符 |
さんじゅうにぶきゅうふ |
1/8拍( |
音符と同じように、表の上にいけばいくほど長く休むことをあらわします。
音符と同じように符点をつけると1.5倍の長さを休むことになります。
例えば、
![]() =
=![]() +
+![]() =1.5拍休み
=1.5拍休み
のような感じです。
音符と違うところは、音符を![]() みたいにくっつけるのではなく、
みたいにくっつけるのではなく、![]() と
と![]() だったら
だったら![]() のようにまとまてしまいます。
のようにまとまてしまいます。
読み方は音符のときと同じように「ふてん~ぶきゅうふ」となります。
補足になりますが、この表の一番上にある全休符![]() は四分音符4つ分(=4拍)のお休みがあるのと同時に、一小節すべてお休みのときにこの全休符
は四分音符4つ分(=4拍)のお休みがあるのと同時に、一小節すべてお休みのときにこの全休符![]() をつけことができます。4拍である必要はありません。
をつけことができます。4拍である必要はありません。
例えば
![]() や
や ![]()
という風に、それぞれ一小節分にあたる長さの休符を書くのもOK ですが、
![]()
のようにしても大丈夫です。
小節線の種類
楽譜を作るときには、拍子のまとまりごとに線を引く決まりがあります。その小節線にも種類があり、用途がそれぞれ違いますので、ここでチェックしておきましょう。
まず、次の譜例を見てください。線がそれぞれ違うので、そこに注意して見てくださいね。
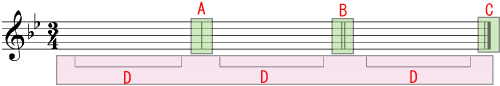
Aの一本線は、「縦線」とよばれるものです。
Bは「複縦線」といって、二本の線でできています。途中で拍子が変わったり、調が変わるときに用いられます。 あと、段落の変わり目でこの線を引くこともあります。
Cは「終止線」といって、太さの違う2本の線でできています。この線を曲の最後で引くと、「ここで曲が終わりますよ」ということを意味します。
音符と休符の仲間はわかりましたか?
拍子
次に拍子について勉強しましょう。拍子とは、リズムの調子を決めるもので、調と同じく、曲の雰囲気が決まります。
まず、読み方と意味から説明します。拍子は、分数(ぶんすう)で表します。
例えば、「3/4拍子」
これはそのまんま「よんぶんのさんびょうし」と読みますが、
1小節に4分音符が3つ入る、という意味になります。
|![]()
![]()
![]() |
|![]()
![]()
![]() |・・・のような感じですね。
|・・・のような感じですね。
つまり、「A/B拍子」といあったら、1小節にB分音符がA個入るという意味です。
例えば、「9/8拍子」 だったら、1小節に8分音符が9個入るということです。
|![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
|![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3/4拍子といっても4分音符しか使ってはいけないという意味ではありません。
1小節に3拍分であれば、例えば、
|![]()
![]()
![]() |
|![]()
![]()
![]() |
|![]()
![]()
・・・のように合計で3拍になっていれば、どんな音符でも使えるんです。
皆さんがどんなメロディーを作ってもちゃんと譜面に書くことができるんですよ。
拍子には、2拍子、3拍子、4拍子、6拍子、9拍子、12拍子などがあり、それぞれ違ったリズムを持っています。
2拍子系 |
3拍子系 |
||
2拍子 |
6拍子 |
3拍子 |
9拍子 |
2/2拍子 |
6/8拍子 |
3/4拍子 |
8/9拍子 |
2/4拍子 |
6/4拍子 |
3/2拍子 |
9/16拍子 |
3/8拍子 |
|||
①2①2 |
①・・②・・ |
①23①23 |
①・・②・・③・・ |
4拍子系 |
|
4拍子 |
12拍子 |
4/4拍子 |
12/8拍子 |
12/16拍子 |
|
①234①234 |
①・・②・・③・・④・・ |
この表の一番下の数字を声に出してみてください。それぞれのリズムの違いが分かると思います。
○で囲んである数字は強く、それ以外は弱く。○が拍の頭です。
ちなみに、
4/4拍子は![]()
2/2拍子は![]() という記号で表しますので、覚えておいて下さい。
という記号で表しますので、覚えておいて下さい。
他にも2拍子と3拍子か組み合わさった「5拍子」や3拍子と4拍子が組み合わさった「7拍子」なんていうのもあります。これらを「変拍子」と言ったりします。
5拍子 |
7拍子 |
5/4拍子 |
7/4拍子 |
5/8拍子 |
7/8拍子 |
①2①23 または ①23①2 |
①23①234 または ①234①23 |